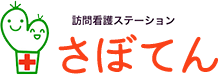訪問看護は、医療的ケアが必要な子どもや病気を抱えた家族にとって、自宅で安心して暮らしていくための大切な支援です。
しかし実際に利用してみると、家族の中には
「看護師さんに来てもらって申し訳ない」
「自分たちでなんとかしなきゃいけないのに…」
といった気持ちを抱えてしまう方も少なくありません。
このような罪悪感は、看護師や他人に対するものだけでなく、子ども本人にまで伝わってしまう可能性があります。
敏感な子どもほど、親の態度や言葉から
「自分は悪いことをしている」
「自分が迷惑をかけている」
と感じ、心を閉ざしてしまうこともあります。
そこでこの記事では、以下のテーマを中心に解説していきます。
-
家族が訪問看護に「申し訳ない」と感じてしまう理由
-
その気持ちが子どもに与える影響
-
親としての関わり方とサポートの工夫
-
子どもの特性や過去のトラウマに合わせた対応
-
我慢が限界に達したときの「爆発」にどう向き合うか
訪問看護を「ありがたい支援」として前向きに受け止め、子どもと家族が安心して過ごすためのヒントをお伝えします。
1. 訪問看護に「申し訳ない」と思ってしまう理由
① 親として「自分がやらなきゃ」という思い
特に母親や父親は、「子どものことは自分が最後まで責任を持たなくてはいけない」という強い思いを抱きがちです。
そのため、看護師に来てもらうことを
「自分がちゃんとできないから頼んでいる」
「親失格なのではないか」
と捉えてしまい、罪悪感を抱くことがあります。
特に母親は、家族や社会から「育児や看護は母親が中心でやるべき」という暗黙のプレッシャーを受けやすく、負担感が強まりやすいです。
② 「他人に迷惑をかけている」という感覚
看護師が訪問する時間は、家族の日常生活の場に他人が入ることになります。
そのため、
「家事が完璧じゃないと恥ずかしい」
「仕事で疲れているのに、来てもらうのは申し訳ない」
と、無意識に「迷惑をかけている」という感覚が強くなるケースがあります。
訪問看護師は専門家であり、サポートが仕事であると分かっていても、心の中で罪悪感が消えない方も多いです。
③ 親の気持ちは子どもに伝わる
親が「申し訳ない」と感じながら訪問看護を受けていると、その感情は表情や態度に表れます。
敏感な子どもほどそれを敏感に察知し、
「自分がいるせいで、お母さんが辛そう」
「自分が悪い子だから、看護師さんが来ているんだ」
と誤解してしまうことがあります。
これは、子どもの心に深い不安や罪悪感を残し、訪問看護自体を嫌がる原因にもなりかねません。
2. 子どもが受け止める「罪悪感」とその影響
子どもは大人以上に感受性が強く、親の気持ちを言葉だけでなく空気や雰囲気で感じ取ります。
特に訪問看護という「特別な出来事」は、子どもにとって大きな出来事であり、心に影響を及ぼしやすいです。
子どもに起こりやすい反応
-
自分の体調を隠すようになる
「具合が悪いと言うと迷惑をかける」と思い、症状を我慢してしまう。 -
訪問看護を嫌がる
看護師が来ること自体をストレスに感じ、拒否や癇癪を起こす。 -
過度に親に気を遣う
「お母さんを困らせたくない」と気持ちを押し殺す。 -
我慢が爆発して突然のパニックや問題行動になる
溜め込んでいた不安や怒りが、限界を超えて一気に出る。
これらは決して「わがまま」や「反抗」ではなく、心のSOSサインです。
3. 家族ができる基本的なサポートの姿勢
① 訪問看護を「前向きなこと」として伝える
親が「申し訳ない」という気持ちでいると、子どもも不安になります。
訪問看護をネガティブな出来事として伝えるのではなく、
「あなたが安心して過ごせるように、手伝ってくれる人が来てくれるんだよ」
「お母さんも少し休めるから、みんなが笑顔でいられるんだよ」
と、プラスの意味を込めて説明することが大切です。
② 子どもの特性に合わせた接し方
子どもは一人ひとり性格や感じ方が異なります。
訪問看護の受け止め方もそれぞれ違うため、柔軟な対応が必要です。
| 子どものタイプ | 特徴 | 親の対応例 |
|---|---|---|
| 親に気持ちを言える子 | 自分の気持ちを言葉にできる | 本人の希望を尊重して看護師に伝える |
| 我慢してしまう子 | 本音を隠して「平気」と言う | 「無理してない?」と優しく確認する |
| 人がいるだけで不安になる子 | 他人が家にいること自体がストレス | 最初は距離を保ち、短時間から慣らす |
| 過去にトラウマがある子 | 医療や人に強制された経験がある | 強制せず、安全な距離感を大切にする |
③ 親は「聴く」姿勢を大切に
子どもが安心して本音を話せる環境を作るには、親が「聴く姿勢」を意識することが重要です。
-
否定せず、最後まで話を聴く
-
「そう思ったんだね」と共感を言葉にする
-
解決策をすぐに出さず、まずは受け止める
子どもは「話を聴いてもらえた」というだけで安心感を得られます。
4. 過去のトラウマや爆発的な感情への理解
訪問看護がトラウマを呼び起こすことも
子どもによっては、訪問看護の存在そのものが過去の嫌な記憶を思い出させることがあります。
例えば、
-
過去に医療処置で強い痛みや恐怖を感じた
-
学校や病院で無理やり行動を制限された
-
親が怒鳴ったり、強く叱られた経験がある
こうした体験は心の奥に残り続け、訪問看護師が来ることで無意識に不安や恐怖が湧き上がることがあります。
我慢が限界に達した時の「爆発」
普段は大人しく見える子でも、我慢を積み重ねることで突然強い怒りやパニックを起こすことがあります。
これは心の限界を超えたサインであり、叱ったり抑え込もうとするのは逆効果です。
親ができること
-
まず安全を確保する(物を投げる、暴れる場合は距離を取る)
-
言葉で落ち着かせようとせず、静かに見守る
-
落ち着いた後で、抱えていた気持ちを少しずつ聴く
5. 看護師との連携で子どもを守る
訪問看護は、家族だけで頑張るものではありません。
看護師と連携することで、子どもの心身をより安全に守ることができます。
伝えておきたい情報
-
子どもの最近の体調や行動の変化
-
訪問前後の気持ちや反応
-
過去に嫌がっていたこと、怖がっていたこと
-
親自身が感じている不安や困りごと
看護師は医療の専門家であり、家族のパートナーでもあります。
情報を共有することで、より安心できるケアが可能になります。
6. 親自身の心を守ることも忘れない
子どもを支える親自身も、常に大きなプレッシャーを抱えています。
親が疲れ果ててしまうと、子どもも安心できません。
親のメンタルケア例
-
週に1回は「自分だけの時間」を確保する
-
相談員や看護師に不安を話す
-
完璧を目指さず「できることだけでいい」と考える
-
夫婦や家族で役割を分担する(母親だけが抱え込まない)
訪問看護は、子どもだけでなく親を含めた家族全体を支えるためのサービスです。
「自分もサポートを受けていい」という気持ちを持ちましょう。
7. まとめ:罪悪感ではなく感謝を
訪問看護を受けるとき、親が「申し訳ない」という気持ちを抱え続けると、子どもはその感情を敏感に察知し、自分を責めてしまいます。
それを防ぐために、
-
訪問看護を「前向きなサポート」として伝える
-
子どもの特性や気持ちに合わせて柔軟に対応する
-
トラウマや爆発のサインを理解して見守る
-
看護師としっかり連携する
-
親自身も心を守る工夫をする
これらを意識していくことが大切です。
訪問看護は「家族を支えるパートナー」。
申し訳ないという気持ちではなく、「ありがとう」という感謝の気持ちで受け入れることで、子どもも安心してケアを受けられるようになります。
家族みんなが少しでも笑顔で過ごせるよう、訪問看護を味方にしていきましょう。