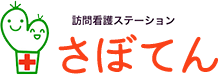「精神訪問看護って言われたけど、正直来てほしくない…」
「無理やり訪問看護を受けさせられることってあるの?」
「精神訪問看護を断ったら、もう支援を受けられないの?」
精神訪問看護は、精神疾患を持つ方が地域で安心して暮らせるように支援する大切なサービスです。
しかし、中には「来てほしくない」「受けたくない」と感じる方もいるかもしれません。
この記事では、精神訪問看護を「来てほしくない」と感じる方が抱える理由を多角的に分析し、
断り方、他の支援の選択肢、知っておくべき制度などを徹底解説します。
あなたの不安や疑問を解消し、より良い選択をするための情報を提供します。

目次
- 精神訪問看護ってどんなもの? 基本を理解する
- 1.1. 精神訪問看護の目的と内容
- 1.2. 精神訪問看護の種類
- 1.3. 精神訪問看護に関わる専門職
- 「精神訪問看護 来てほしくない」と感じる6つの理由
- 2.1. プライバシーへの懸念
- 2.2. 拒否したい、受け入れたくない気持ち
- 2.3. 経済的な理由
- 2.4. 過去のトラウマや不信感
- 2.5. 自立への願望
- 2.6. その他、個別の事情
- 精神訪問看護を断る前に知っておくべきこと
- 3.1. 精神保健福祉法の理解
- 3.2. 医療観察法の理解
- 3.3. 断ることで生じる可能性のある影響
- 精神訪問看護を断る方法と伝えるべきこと
- 4.1. 主治医、ケースワーカー、訪問看護ステーションへの伝え方
- 4.2. 家族や支援者への相談
- 4.3. 断る際の注意点
- 精神訪問看護以外にもある! あなたを支える支援の選択肢
- 5.1. 外来での精神科受診
- 5.2. デイケア、作業所などの利用
- 5.3. 地域活動支援センターの利用
- 5.4. 相談支援専門員によるサポート
- 5.5. ピアサポート
- 精神訪問看護を改めて検討するタイミング
- 6.1. 症状悪化による生活への支障
- 6.2. 退院後の社会生活への不安
- 6.3. 家族や支援者の負担増
- よくある質問Q&A:「精神訪問看護 来てほしくない」と感じている方からの質問
- まとめ:精神訪問看護は「選択肢」の一つ。 あなたに合った支援を見つけましょう。
-
精神訪問看護ってどんなもの? 基本を理解する
精神訪問看護を理解することで、「来てほしくない」と感じる理由が明確になり、冷静な判断ができるようになります。
1.1. 精神訪問看護の目的と内容
精神訪問看護は、精神疾患を持つ方が、住み慣れた地域で安心して生活を送れるように支援するサービスです。看護師や精神保健福祉士などの専門職が、ご自宅を訪問し、以下のような支援を行います。
- 症状の観察と助言: 病状の変化を把握し、必要な情報提供や相談を行います。
- 服薬管理: 正しい服薬を促し、副作用の相談にも応じます。
- 日常生活の支援: 食事、入浴、掃除など、日常生活を送るためのサポートを行います。
- 社会生活への支援: 地域社会とのつながりを保ち、社会復帰を支援します。
- 家族への支援: 家族への相談対応や情報提供、関係機関との連携を行います。
1.2. 精神訪問看護の種類
精神訪問看護には、医療保険が適用される「医療保険精神科訪問看護」と、介護保険が適用される「介護保険精神科訪問看護」があります。適用条件や利用できるサービス内容が異なるため、自身の状況に合わせて選択する必要があります。
1.3. 精神訪問看護に関わる専門職
精神訪問看護には、以下のような専門職が関わります。
- 看護師: 医療的なケアや日常生活の支援を行います。
- 精神保健福祉士: 社会生活への支援や関係機関との連携を行います。
- 作業療法士: 日常生活技能の訓練や社会復帰支援を行います。
- 医師: 訪問看護計画の作成や指示、医療的な判断を行います。
-
「精神訪問看護 来てほしくない」と感じる6つの理由
精神訪問看護を「来てほしくない」と感じる理由は人によって様々ですが、主に以下のようなものが考えられます。
2.1. プライバシーへの懸念
自宅に他人が入ることへの抵抗感や、自分の生活や病状を知られることへの不安から、訪問看護を避けたいと感じる場合があります。
2.2. 拒否したい、受け入れたくない気持ち
病気を受け入れたくない、他人に干渉されたくない、といった心理的な理由から、訪問看護を受けたくないと感じる場合があります。
2.3. 経済的な理由
訪問看護の利用料金が負担になる、または利用できる制度をよく知らないといった理由から、訪問看護を避けたいと感じる場合があります。
2.4. 過去のトラウマや不信感
過去の医療機関や支援者との関係で、辛い経験をしたり、不信感を抱いたりしたことが、訪問看護を拒否する原因となる場合があります。
2.5. 自立への願望
自分で生活できると思っている、他人の助けを借りたくない、といった自立への強い思いから、訪問看護を必要としないと感じる場合があります。
2.6. その他、個別の事情
上記以外にも、家庭の事情、生活リズム、過去の支援内容など、個々の状況によって様々な理由が考えられます。
-
精神訪問看護を断る前に知っておくべきこと
精神訪問看護を断ることは可能ですが、断る前に知っておくべき重要な点があります。
3.1. 精神保健福祉法の理解
精神保健福祉法は、精神疾患を持つ方の権利擁護と社会参加促進を目的とした法律です。この法律に基づいて、医療機関や行政機関は、必要な場合に訪問看護を勧めることがあります。
3.2. 医療観察法の理解
医療観察法は、重大な他害行為を行った精神疾患を持つ方の社会復帰を支援するための法律です。この法律に基づいて、裁判所が、対象者に対して訪問看護を含む処遇を決定する場合があります。
3.3. 断ることで生じる可能性のある影響
訪問看護を断ることで、以下のような影響が出る可能性があります。
- 症状悪化のリスク: 定期的な観察や支援を受けられず、症状が悪化する可能性があります。
- 社会生活への支障: 孤立や社会参加の困難さから、生活の質が低下する可能性があります。
- 医療・福祉サービスの利用制限: 必要な医療や福祉サービスを受けられなくなる可能性があります。
- 精神訪問看護を断る方法と伝えるべきこと
精神訪問看護を断る場合、適切な方法と伝え方で、相手に理解してもらうことが大切です。
4.1. 主治医、ケースワーカー、訪問看護ステーションへの伝え方
- 正直な気持ちを伝える: 「訪問看護を受けることに抵抗がある」「今は必要ないと感じている」など、自分の気持ちを正直に伝えましょう。
- 具体的な理由を説明する: プライバシーへの懸念、過去のトラウマ、自立への願望など、断る理由を具体的に説明すると、相手も理解しやすくなります。
- 代替案を提案する: 訪問看護以外の支援を希望する場合は、その旨を伝え、代替案を提案しましょう。
- 感情的にならない: 感情的に反発するのではなく、冷静に話し合う姿勢が大切です。
4.2. 家族や支援者への相談
訪問看護を断ることを検討している場合は、家族や支援者にも相談しましょう。
あなたの状況を理解してくれるかもしれませんし、客観的な意見やアドバイスをもらえるかもしれません。
4.3. 断る際の注意点
- 一方的に断らない: 訪問看護を一方的に拒否するのではなく、よく話し合い、理解を得るように努めましょう。
- 丁寧な言葉遣いを心がける: 感謝の気持ちや配慮を示すことで、良好な関係を保つことができます。
- 記録を残す: 話し合いの内容や決定事項を記録しておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。
-
精神訪問看護以外にもある! あなたを支える支援の選択肢
精神訪問看護以外にも、あなたを支える支援の選択肢はたくさんあります。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったものを選びましょう。
5.1. 外来での精神科受診
定期的な診察やカウンセリングを受けたい方、薬物療法を中心に治療を進めたい方に適しています。
5.2. デイケア、作業所などの利用
仲間との交流やプログラムへの参加を通じて、社会生活技能の回復や社会参加を目指したい方に適しています。
5.3. 地域活動支援センターの利用
地域交流スペースの利用やレクリエーション活動への参加など、地域で孤立せずに生活するためのサポートを受けたい方に適しています。
5.4. 相談支援専門員によるサポート
福祉サービスの利用に関する相談や、自立した生活を送るための支援計画の作成など、総合的なサポートを受けたい方に適しています。
5.5. ピアサポート
同じような経験を持つ仲間(ピア)からの支援を受けることで、孤独感を軽減したり、回復への希望を見出したりすることができます。
-
精神訪問看護を改めて検討するタイミング
現時点では訪問看護を必要としないと感じている方も、状況によっては、再度検討する必要が出てくる場合があります。
6.1. 症状悪化による生活への支障
症状が悪化し、日常生活を送ることが困難になった場合は、訪問看護の利用を検討しましょう。専門職のサポートを受けることで、生活の安定を取り戻せる場合があります。
6.2. 退院後の社会生活への不安
入院から退院後、社会生活にスムーズに戻れるか不安を感じる場合は、訪問看護の利用を検討しましょう。社会復帰に向けたサポートを受けることで、自信を持って生活できるようになる場合があります。
6.3. 家族や支援者の負担増
家族や支援者の負担が大きくなっている場合は、訪問看護の導入を検討しましょう。訪問看護を活用することで、家族や支援者の負担を軽減し、より良い関係を築ける場合があります。
-
よくある質問Q&A:「精神訪問看護 来てほしくない」と感じている方からの質問
Q1. 精神訪問看護は強制的に受けなければならないのですか?
A1. 精神保健福祉法に基づき、医療機関や行政機関が訪問看護を勧めることはありますが、
基本的にはご自身の意思で利用するかどうかを決定できます。
ただし、医療観察法に基づいて裁判所が処遇として訪問看護を決定した場合は、原則として従う必要があります。
Q2. 精神訪問看護を断ると、今後の医療や福祉サービスに影響が出ますか?
A2. 訪問看護を断ったこと自体が、直ちに他の医療や福祉サービスの利用に影響するわけではありません。
しかし、症状が悪化して入院が必要になったり、自立した生活が困難になったりする場合には、
必要なサービスを受けられなくなる可能性があります。
Q3. 訪問看護ステーションを変えることはできますか?
A3. 訪問看護ステーションの変更は可能です。
サービス内容やスタッフとの相性などを考慮して、より自分に合ったステーションを選びましょう。
Q4. 費用が心配なのですが、相談できますか?
A4. 医療保険や介護保険の適用状況、自己負担額などについては
医療機関や訪問看護ステーション、地域の相談窓口などで相談できます。
Q5. 訪問看護に来る人(看護師や精神保健福祉士)を選べますか?
A5. 訪問看護ステーションによっては、指名制度がある場合があります。
希望がある場合は、訪問看護ステーションに相談してみましょう。
-
まとめ:精神訪問看護は「選択肢」の一つ。 あなたに合った支援を見つけましょう。
精神訪問看護は、精神疾患を持つ方が地域で安心して生活を送るための有効な支援手段の一つです。
しかし、「来てほしくない」と感じる場合は、その理由をしっかりと見つめ、
この記事で紹介した情報を参考に、あなたにとって最適な選択をしてください。
様々な支援があることを知り、遠慮なく専門家に相談することも大切です。
ご相談・お問い合わせ
もしこの記事を読んで、「少しでも気になる」と感じたら、お気軽にご相談ください。
〒358-0035 埼玉県入間市中神645-3 中村アトリエ5号室
TEL:04-2946-7317